が,新設の医科大学で医化学講座を担当できるのは荒木寅三郎以外にはなく,したがって33歳の若さでの抜擢となった。
 当初医化学教室は,現在の時計台の位置にあった第三高等学校の旧校舎の中にあり,そこで,初代助手若山昇三とともに10名の学生を相手に講義と実習が始まった。やがて,岡山時代の門下生数名(後の国立栄養研究所初代所長佐伯
矩を含む)や東京帝大を卒業したばかりの井上嘉都治,さらには大阪府立医学校を卒業した古武弥四郎が参加して陣容が整った。明治36(1903)年にいたり,現在の医学部構内の管理棟と
D 棟の位置に L 字型木造二階建ての医化学教室,講義室,実習室が建築されるにおよび,新教室において本格的な教育・研究が開始されることになった。この年,井上が助教授となり,荒木教授自身も医科大学長(学部長)に就任している。この頃から荒木教授の名声を慕って全国各地から人が集まり始め,京都帝大医科の卒業生も吉光寺錫(明治38年第3回卒業生)を先頭に,毎年数名ずつ相次いで教室に入ってくるようになった。また臨床各科からも医化学教室の門をたたく者が絶えなかった。さらに時代が下ると,京都帝大医科の古い卒業生の中にも大学院生として医化学教室に籍を置く者も少なくなかった。大正
2(1913)年に井上助教授が東北帝大医学部の創設に備えて仙台医専教授に転出するにおよび,助教授は吉川順治(明治40年京都帝大医卒)が後を嗣いだが,大正4(1915)年に荒木教授が京都帝大の第7代総長に決まったため,教室に大きな人事異動が行われることになった。
当初医化学教室は,現在の時計台の位置にあった第三高等学校の旧校舎の中にあり,そこで,初代助手若山昇三とともに10名の学生を相手に講義と実習が始まった。やがて,岡山時代の門下生数名(後の国立栄養研究所初代所長佐伯
矩を含む)や東京帝大を卒業したばかりの井上嘉都治,さらには大阪府立医学校を卒業した古武弥四郎が参加して陣容が整った。明治36(1903)年にいたり,現在の医学部構内の管理棟と
D 棟の位置に L 字型木造二階建ての医化学教室,講義室,実習室が建築されるにおよび,新教室において本格的な教育・研究が開始されることになった。この年,井上が助教授となり,荒木教授自身も医科大学長(学部長)に就任している。この頃から荒木教授の名声を慕って全国各地から人が集まり始め,京都帝大医科の卒業生も吉光寺錫(明治38年第3回卒業生)を先頭に,毎年数名ずつ相次いで教室に入ってくるようになった。また臨床各科からも医化学教室の門をたたく者が絶えなかった。さらに時代が下ると,京都帝大医科の古い卒業生の中にも大学院生として医化学教室に籍を置く者も少なくなかった。大正
2(1913)年に井上助教授が東北帝大医学部の創設に備えて仙台医専教授に転出するにおよび,助教授は吉川順治(明治40年京都帝大医卒)が後を嗣いだが,大正4(1915)年に荒木教授が京都帝大の第7代総長に決まったため,教室に大きな人事異動が行われることになった。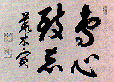 京都帝大の総長は創立以来政府が任命してきたが,法科教授会が大学の自治を求め,いわゆる澤柳事件が起こり,これを契機として学内から総長を選ぶ機運が盛り上がり,荒木教授が初めて公選により総長に選出されたのである。これは全学の大学人が,36歳の若さで医科大学長になり,10年以上学部管理の職にあった荒木寅三郎の行政的手腕を高く評価したためであろう。以来昭和
4(1929)年まで4期15年にわたり繰り返し総長に再選され,現在の京都大学の礎を築いた。
京都帝大の総長は創立以来政府が任命してきたが,法科教授会が大学の自治を求め,いわゆる澤柳事件が起こり,これを契機として学内から総長を選ぶ機運が盛り上がり,荒木教授が初めて公選により総長に選出されたのである。これは全学の大学人が,36歳の若さで医科大学長になり,10年以上学部管理の職にあった荒木寅三郎の行政的手腕を高く評価したためであろう。以来昭和
4(1929)年まで4期15年にわたり繰り返し総長に再選され,現在の京都大学の礎を築いた。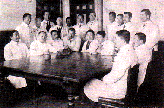 荒木教授の総長就任と同時に後任教授の選考が行われ,助手の前田
鼎(明治44年京都帝大医卒)が抜擢され,助教授に昇任の上米国へ留学したのち教授に任命されることが教授会で申し合わされた。教授不在中の医化学講座は,薬物学講座の森島庫太教授が兼担した。講義は,京都府立医専教授に転出した吉川前助教授が受け持ち,助教授の席は山口幸助(大正元年京都帝大医卒)が当分の間引き継いだ。前田助教授の出発から帰任までの約3年半の間は,荒木総長が,医化学教室の裏にある総長官舎から出勤の途中や帰宅時に研究室に立ち寄り,教室全体の動静や研究の進展を点検した。
荒木教授の総長就任と同時に後任教授の選考が行われ,助手の前田
鼎(明治44年京都帝大医卒)が抜擢され,助教授に昇任の上米国へ留学したのち教授に任命されることが教授会で申し合わされた。教授不在中の医化学講座は,薬物学講座の森島庫太教授が兼担した。講義は,京都府立医専教授に転出した吉川前助教授が受け持ち,助教授の席は山口幸助(大正元年京都帝大医卒)が当分の間引き継いだ。前田助教授の出発から帰任までの約3年半の間は,荒木総長が,医化学教室の裏にある総長官舎から出勤の途中や帰宅時に研究室に立ち寄り,教室全体の動静や研究の進展を点検した。荒木研究室の研究業績には,まず,荒木教授のストラスブルグ時代の学位論文となった「酸素欠乏時における動物体内乳酸生成」に関連するものが挙げられる。Pasteur が酵母の実験から嫌気条件下で酪酸が多量に生成することを見いだしたことは今日でもよく知られているが,動物実験でこれと似たことを初めて示したのが荒木教授であることは意外に知られていない。医化学教室では,動物の組織を自家融解にかけると乳酸が次第に蓄積するが,その立体構造が L (+) 型であることを決定し,また,筋肉の無細胞抽出液においても乳酸の生成が行われることより,乳酸生成は酵素作用であろうと推定しているが,これらはきわめて先駆的な仕事である。さらに,荒木教授が腸粘膜から DNase を発見したこともあまり知られていないが,これは,京都帝大着任後明治35(1902)〜36(1903)年の欧州旅行の際に,ハイデルベルグの Albrecht Kossel のもとで行った研究による。医化学教室では,さらに各種生物や組織から分離した核酸の化学分析および核酸分解酵素の研究,鶏卵の孵化時における物質代謝を解析する研究も多くなされた。また,かびの化学組成,大脳の化学成分,米糠中のビタミンというようなテーマが見受けられ,極めて多彩である。
医化学教室からの発表論文は約100編あり,ほとんどすべてがドイツ語で,Hoppe-Seyler's Zeitschrift fuer Physiologische Chemie と Biochemische Zeitschrift に掲載されている。Hoppe-Seyler 誌が多いのは,荒木教授の恩師とのつながりからみて当然とも思われるが,研究の質の高さがこれを可能にしたと考えてよい。荒木教授はストラスブルグ時代に Hoppe-Seyler 教授からこの雑誌の校正をまかされた経験をもち,ドイツ語に堪能であった。大正 3 ( 1914 )
年に第一次世界大戦が勃発して,ヨーロッパからの交通が途絶え,米国から図書や薬品類が輸入されるのみとなると,ドイツの雑誌への論文発表が困難となり,そのころ始まった京都帝国大学医科大学紀要(独文)や米国の Journal of Biological Chemistry に論文が発表された。
荒木教授は講義では,悠々迫らぬ態度で教壇に立ち,ノートなしに極めてゆっくり理路整然と話をし,学生の間でも評判が高かった。また,研究室においては,常に温顔をもって懇切丁寧に指導し,教室員の尊敬をあつめた。20代の頃,荒木教授は大澤謙二教授が主宰する帝国大学医科大学生理学教室で学んだが,Hoppe-Seyler の教科書についての疑問点に答えてくれる者がないことから,直接著者に教わる必要があると考え,私費をもって渡欧したといわれている。物事を徹底的に追及する態度が研究にも表われ,すばらしい成果を上げたものと思われる。また,それ故に後進の指導にも適切で行き届いたものがあったのであろう。
 荒木一門からは,古武弥四郎(大阪帝大),井上嘉都治(東北帝大)等の医科生化学教授の外,戸田正三(京都(帝)大医衛生学,後に金沢大学学長),佐武安太郎(東北帝大医生理学)等の他分野の教授も出ている。また,佐伯
矩(国立栄養研究所長)のような行政的な研究機関の開拓者や,戸谷銀三郎(大連病院副院長,後に名古屋市大学長),守中 清(大連病院院
荒木一門からは,古武弥四郎(大阪帝大),井上嘉都治(東北帝大)等の医科生化学教授の外,戸田正三(京都(帝)大医衛生学,後に金沢大学学長),佐武安太郎(東北帝大医生理学)等の他分野の教授も出ている。また,佐伯
矩(国立栄養研究所長)のような行政的な研究機関の開拓者や,戸谷銀三郎(大連病院副院長,後に名古屋市大学長),守中 清(大連病院院長,後に満州医大学長),佐藤剛蔵(京城帝大医医化学教授,後に京城医専校長)のように大陸や半島において活躍する人たちも出て,多士済済である。また,荒木教授が医科大学長在職中に,佐々木隆興博士を京都帝大内科学教授に招聘したことは,わが国の生化学の発展において極めて意義深いことであった。佐々木博士は大正13(1924)年と昭和11(1936)年の2度にわたり学士院賞を受賞した。
日露戦争から第一次世界大戦の終わりまでのわが国学術の勃興期に,医学の中でも基礎的で地味な分野である生化学の研究・教育において,日本の指導的立場に立つ研究グループを形作ったのが荒木寅三郎の医化学教室であった。(中 澤 淳 記)