【筆頭著者紹介】
 古瀬幹夫博士は、現在教室の助手。 京大生物物理の修士課程を経て、シオノギ
の研究所に就職するが、思うところあり退職して月田グループが生理研にいる時
に博士課程に入る。 緻密で論理的な実験には周囲が舌をまくが、妻と生まれた
ばかりの長男を京都に残して、単身岡崎で頑張るという背水の陣が、オクルディ
ンの発見につながる。 さらに、昨年、長女が生まれ、本論文のクローディンを
発見する。 どうも、子供が生まれると大きな発見をするらしい。 「しばらく
たったらまた子供を生まなくちゃ」と、奥さんが言っているとかいないとか。
古瀬幹夫博士は、現在教室の助手。 京大生物物理の修士課程を経て、シオノギ
の研究所に就職するが、思うところあり退職して月田グループが生理研にいる時
に博士課程に入る。 緻密で論理的な実験には周囲が舌をまくが、妻と生まれた
ばかりの長男を京都に残して、単身岡崎で頑張るという背水の陣が、オクルディ
ンの発見につながる。 さらに、昨年、長女が生まれ、本論文のクローディンを
発見する。 どうも、子供が生まれると大きな発見をするらしい。 「しばらく
たったらまた子供を生まなくちゃ」と、奥さんが言っているとかいないとか。
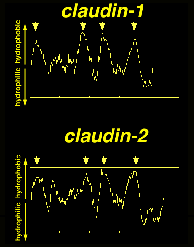 斉藤らによるオクルディンのノックアウトの結果、タイトジャンクション
がオクルディンなしでも形成されることが示されました (研究室ニュー
スの項参照)。 そこで、我々の研究室の根本である単離ジャンクション
分画から、未知のタイトジャンクション膜蛋白質を捜そうとしました。
この分画をソニケーションと蔗糖密度遠心法でさらに分画し、その時に
オクルディンと挙動をともにする膜蛋白質を追求した結果、分子量22kD
のやはり4回膜貫通蛋白質(左図)を同定することができました。 2種類
のアイソタイプ(38% identical)が同定でき、それぞれクローディン(
Claludin)ー1およびー2と名付けました。
斉藤らによるオクルディンのノックアウトの結果、タイトジャンクション
がオクルディンなしでも形成されることが示されました (研究室ニュー
スの項参照)。 そこで、我々の研究室の根本である単離ジャンクション
分画から、未知のタイトジャンクション膜蛋白質を捜そうとしました。
この分画をソニケーションと蔗糖密度遠心法でさらに分画し、その時に
オクルディンと挙動をともにする膜蛋白質を追求した結果、分子量22kD
のやはり4回膜貫通蛋白質(左図)を同定することができました。 2種類
のアイソタイプ(38% identical)が同定でき、それぞれクローディン(
Claludin)ー1およびー2と名付けました。
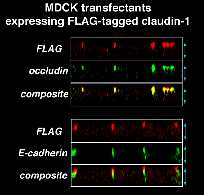 これらのクローディンにFLAGタグをつけ、培養上皮細胞に導入
したところ、どちらも左図のコンフォーカル顕微鏡像で明らかなよ
うに、タイトジャンクションにオクルディンとともに濃縮しました。
このことは、電子顕微鏡でも確認されました。 クローディンには、
さらに似た仲間がいるらしいこともあり、タイトジャンクション
の分野は新しい局面を迎えたと言えそうです。
これらのクローディンにFLAGタグをつけ、培養上皮細胞に導入
したところ、どちらも左図のコンフォーカル顕微鏡像で明らかなよ
うに、タイトジャンクションにオクルディンとともに濃縮しました。
このことは、電子顕微鏡でも確認されました。 クローディンには、
さらに似た仲間がいるらしいこともあり、タイトジャンクション
の分野は新しい局面を迎えたと言えそうです。
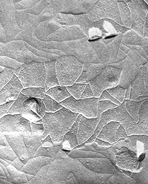 そこで、次の論文では、クローディンー1またはー2のcDNAを、マウスL
線維芽細胞に導入してみました。 ステーブルトランスフェクタントをとって
調べたところ、驚いたことに、その細胞間に左図に示したような巨大なタイト
ジャンクションストランドのネットワークが形成されていることが分かりまし
た。 一方、オクルディンのみをL細胞に導入したところ、きわめて短いスト
ランドは形成されるものの、クローディンのような巨大なタイトジャンクショ
ンを作ることはありませんでした。 そこで、L細胞にクローディンー1とオ
クルディンを共発現させてみました。 すると、クローディンとオクルディン
は共重合し、大きなネットワークを作ることが分かりました。
そこで、次の論文では、クローディンー1またはー2のcDNAを、マウスL
線維芽細胞に導入してみました。 ステーブルトランスフェクタントをとって
調べたところ、驚いたことに、その細胞間に左図に示したような巨大なタイト
ジャンクションストランドのネットワークが形成されていることが分かりまし
た。 一方、オクルディンのみをL細胞に導入したところ、きわめて短いスト
ランドは形成されるものの、クローディンのような巨大なタイトジャンクショ
ンを作ることはありませんでした。 そこで、L細胞にクローディンー1とオ
クルディンを共発現させてみました。 すると、クローディンとオクルディン
は共重合し、大きなネットワークを作ることが分かりました。
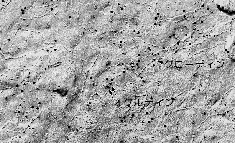 最後の図は、このようなL細胞から凍結割断レプリカを
とり、クローディン(5nm)とオクルディン(15nm)
で2重ラベルしたものです。 生体の中でも、数種類の
クローディンと一種類のオクルディンが共重合してスト
ランドを作っていると考えられます。
最後の図は、このようなL細胞から凍結割断レプリカを
とり、クローディン(5nm)とオクルディン(15nm)
で2重ラベルしたものです。 生体の中でも、数種類の
クローディンと一種類のオクルディンが共重合してスト
ランドを作っていると考えられます。