私たちの細胞間接着装置分画から生まれた、最大の成果は、今のところ、オクルディン、クローディンの発見に始まる「タイトジャンクションの分子生物学的解析」です。この一連の研究により「バリアーの分子生物学」とでも呼ぶべき、新しい分野が開けてきました。この研究に関しては、2000年の「生化学」の総説 (このページ)、2001年の「Nature Review Mol.Cell Biol.」の総説(ここをクリック)、そして2003年のある講演会の記録(ここをクリック)をお読み下さい。全体像が分かっていただけると思います。
「生化学」2000年3月号 掲載
タイトジャンクションを構成する4回膜貫通型蛋白質
オクルディンとクローディンの発見:
Paracellular Pathwayの新しい生理学へ向けて
月田承一郎・古瀬幹夫
タイトジャンクションは、上皮細胞シートや内皮細胞シートにおいて、細胞間をシールする重要な細胞間接着装置であるが、一方で、このジャンクションを横切って物質が細胞間の通路(paracellular pathway)を運ばれることも知られている。 タイトジャンクションにおいて隣合う細胞膜をゼロの距離にまで近づけている接着分子の実体は長い間謎に包まれていたが、最近になってようやく、4回膜貫通型蛋白質であるオクルディンとクローディンが同定された。 この発見によって、タイトジャンクションの機能を分子生物学的手法を用いて解析することが可能となり、新しいparacellular pathwayの生理学が生まれようとしている。
1.はじめに
多数の細胞が機械的に結びつけられている多細胞生物の形作りにおいて、細胞間および細胞基質間の接着の果たす役割は大きい。 多様な接着分子が、機械的な結合(接着)だけでなく、特異的な細胞認識や複雑な接着シグナルの伝達にもかかわっていることが、次々と明らかにされている。 しかし、これらとは全く別の観点から、細胞間の接着が多細胞生物にとって本質的に重要であることが古くから知られている。 それは、「細胞間を通った物質の移動(漏れ)の制御」という観点である。
多細胞生物は上皮細胞に囲まれることにより、まず、自己の内と外に区別される。 そして、体の中は、上皮細胞や内皮細胞のシートにより、さらにいくつもの部屋に分けられている。 脳、血管、腎臓の尿細管などはその代表的な部屋であるが、特殊なものでは甲状腺の濾胞、内耳の蝸牛管なども挙げられる。 部屋の中のイオン環境や蛋白質の種類・濃度などは、それぞれの機能に応じて大きく異なっており、この環境を動的に保っていることが、多細胞生物が生きていく上で必要不可欠である。 しかし、多細胞生物であるが故に、これらの部屋を仕切る壁は細胞を並べて作らざるを得ないが、いくらカドヘリンなどの強力な接着分子で細胞間を結合させても、水・イオン・蛋白質などは細胞間を自由に通ることができる。 そこで、多細胞生物が存在するためには、この細胞間を通った物質の移動(漏れ)を防ぐための特殊な接着機構が必要となる。 それが後述するタイトジャンクション(以下TJ)と呼ばれる接着装置で、ここでは隣り合う細胞の細胞膜の距離がゼロにまで近づいていて、細胞間を通った物質の移動を防いでいる。
脊椎動物では、このTJを上皮細胞間や内皮細胞間に発達させることにより、これらの細胞シートが各部屋の環境を守るバリアーとして働くことを可能としている。 しかし、先にも述べたように、各部屋の内部の環境は静的に保たれているのではなく、部屋の外と物質の交換をしながら動的に保たれている。 この際、いろいろな物質が細胞シートを横切る必要があるが、それには図1に示すような2つのルートがある。 細胞そのもの、すなわち細胞膜そのものを横切って運ばれるルートはtranscellular
pathwayと呼ばれ、ここには多くのチャネル分子やポンプ、トランスポーターなどがかかわっている。
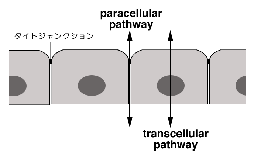 このpathwayはこれまでの生理学研究の中心的テーマであった。 一方、細胞間、すなわちTJを横切って運ばれるルートはparacellualr
pathwayと呼ばれる。 TJがバリアーのために存在するという、先の議論と一見矛盾するようであるが、実際にはTJのバリアー機能は、きわめてtightなものから、かなりleakyなものまで相当の幅があり、一般的にTJは選択的にイオンなどを通しうるバリアーであると言うことができる。 すなわちTJはparacellular
channelとでも言うべき“穴”を内包すると考えられるのである1)。 物質によっては主にparacellular pathwayを通って部屋の内外で交換されることも知られており、このpathwayもtranscellualr
pathwayと同様に重要であると考えられてきた。 しかし、TJの分子的基盤に関する我々の知識がきわめて未熟であったために、その解析は遅れていた2)。
このpathwayはこれまでの生理学研究の中心的テーマであった。 一方、細胞間、すなわちTJを横切って運ばれるルートはparacellualr
pathwayと呼ばれる。 TJがバリアーのために存在するという、先の議論と一見矛盾するようであるが、実際にはTJのバリアー機能は、きわめてtightなものから、かなりleakyなものまで相当の幅があり、一般的にTJは選択的にイオンなどを通しうるバリアーであると言うことができる。 すなわちTJはparacellular
channelとでも言うべき“穴”を内包すると考えられるのである1)。 物質によっては主にparacellular pathwayを通って部屋の内外で交換されることも知られており、このpathwayもtranscellualr
pathwayと同様に重要であると考えられてきた。 しかし、TJの分子的基盤に関する我々の知識がきわめて未熟であったために、その解析は遅れていた2)。
2. タイトジャンクションの構造
単層の上皮細胞では、隣り合う細胞膜(ラテラル膜)のもっともアピカルよりに細胞間接着装置複合体と呼ばれる領域があり、その部分で隣り合う細胞が強く接着している(図2A)。 この領域は3つに分かれ、アピカル側からタイトジャンクション(TJ)、アドヘレンスジャンクション(AJ)、デスモソーム(DS)と呼ばれる3)。 AJにはカドヘリンが接着分子として濃縮しており、よく発達した裏打ち構造を介してアクチンフィラメントが密に細胞膜に結合している。 DSでもやはりカドヘリン様の接着分子が機能しており、ここ
 では中間径フィラメントが結合している。 これら2つの接着装置では向かい合う細胞膜間の距離は15-20 nmに保たれている。 細胞間の強い機械的結合を担っており、その結合力を細胞骨格につなげることにより、組織全体としての機械的強度をも担っている。 これらに較べ、TJは特殊な接着装置である。 超薄切片像で見ると、ところどころで向かい合う細胞膜間の距離がゼロにまで近づいている3)(TJのキッシングポイントと呼ばれる)(図2B)。 また、凍結割断レプリカ法で観察すると、TJの部分では、膜内粒子が一列に並んだストランド(TJストランド)が編み目を構成している4)(図2C)。 このような観察から、TJの構造は図2Aのようなものであると想像されてきた。 すなわち、何らかの内在性膜蛋白質が細胞膜の中で線状に重合してTJストランドを形成し、向かい合う細胞膜中のTJストランドと側面で対合することによりキッシングポイントを形成するという構造である。 しかし、このTJストランドを構成する内在性膜蛋白質の実体は長い間謎に包まれており、TJストランドが特殊な脂質の逆ミセルから出来ているという脂質説も有力視されて続けてきた5)。
では中間径フィラメントが結合している。 これら2つの接着装置では向かい合う細胞膜間の距離は15-20 nmに保たれている。 細胞間の強い機械的結合を担っており、その結合力を細胞骨格につなげることにより、組織全体としての機械的強度をも担っている。 これらに較べ、TJは特殊な接着装置である。 超薄切片像で見ると、ところどころで向かい合う細胞膜間の距離がゼロにまで近づいている3)(TJのキッシングポイントと呼ばれる)(図2B)。 また、凍結割断レプリカ法で観察すると、TJの部分では、膜内粒子が一列に並んだストランド(TJストランド)が編み目を構成している4)(図2C)。 このような観察から、TJの構造は図2Aのようなものであると想像されてきた。 すなわち、何らかの内在性膜蛋白質が細胞膜の中で線状に重合してTJストランドを形成し、向かい合う細胞膜中のTJストランドと側面で対合することによりキッシングポイントを形成するという構造である。 しかし、このTJストランドを構成する内在性膜蛋白質の実体は長い間謎に包まれており、TJストランドが特殊な脂質の逆ミセルから出来ているという脂質説も有力視されて続けてきた5)。
3.オクルディンの同定と機能解析
我々は、もともと、カドヘリンが機能するAJの分子構築を明らかにするために、AJが濃縮した分画を肝臓から単離する方法を開発していた6)。 そして、詳細は省略するが、ZO−1と呼ばれる細胞膜裏打ち蛋白質のcDNAクローニングの過程で、この分画にTJも極度に濃縮していることに気づいた7)。 もし、TJストランドが内在性膜蛋白質によって構成されているのであれば、そのような蛋白質もこの分画に濃縮している筈である。 そこでこの単離分画を抗原にしてモノクローナル抗体を得ることにより、TJストランドを構成する膜蛋白質の同定を試みることにした。 実際には高い抗原性を得るために、ヒヨコの肝臓から分画を得て、それをラットに免疫することにより多数のモノクローナル抗体を得た。 その中からTJの膜蛋白質を認識する可能性のあるモノクローナル抗体を絞り込んだところ、分子量65kDaぐらいの幅広いバンドを認識するものが3種類とれた。 これらの抗体は電子顕微鏡レベルでTJストランドそのものを認識した。 また、その抗原が内在性膜蛋白質であることも生化学的に確認できた。 そこでこの抗原をオクルディン(occludin:ラテン語のocclude、閉じるの意、から)と名付け、そのcDNAを単離したところ、新規の4回膜貫通型蛋白質であることが明らかになった8)。 図3に示すように、オクルディンはそのN末端側半分にそれぞれ約40アミノ酸からなる2つの細胞外ループを持つが、特に第一ループの約70%のアミノ酸がチロシンかグリシンという奇妙な構造をしていた。 このようにして、TJストランドを構成する膜蛋白質として、ニワトリのオクルディンが初めて同定されたのは、1993年の暮れのことで、TJの構造と機能の理解が一気に進むかと思われた2)。 しかし、実際には、オクルディンのアミノ酸配列が種間で大きく変動していたために、マウスやヒトのオクルディンの同定は難航した。 徐々に充実してきた遺伝子のデータベースの中から、我々が幸運にもヒトのオクルディンの一部の配列を見つけ、ようやくほ乳類のオクルディンの同定に成功するまでに約2年の時間が必要であった9)。
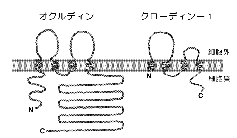
一方で、ニワトリではあるが、TJの内在性膜蛋白質が見つかったということで、多くの研究室でオクルディンの機能解析が始まった。 その結果、オクルディンがTJストランドの形成を通して、TJの機能を直接担っているということを主張する論文が次々と発表されるようになった10)。 しかし、我々は、本当にオクルディンだけでTJストランドが形成されているのかどうかについて、徐々に疑問を持つようになってきた。 このような疑問に直接答える一つの方法は、オクルディンの遺伝子をノックアウトすることである。 そこで、マウスのオクルディン遺伝子の単離に成功した後に、相同組み換えを利用してES(embryonic
stem)細胞においてオクルディンの遺伝子をダブルノックアウトした。 その細胞を試験館内で上皮細胞に分化させたところ、予想外なことに、オクルディンを発現しないこのような上皮細胞でも立派なTJストランドのネットワークが形成された11)。 この事実は、オクルディンがなくてもTJストランドが形成されるということを意味していた。
4.クローディン−1、−2の同定
このように遺伝子を破壊してもフェノタイプに変化がない場合は、オクルディン遺伝子がファミリーを形成していて、他のメンバーが代わりをするためと考えるのが普通である。 しかし、オクルディンに関しては、データベース上も、RT−PCR等による検索上も、似たアミノ酸配列を持つ膜蛋白質は見つからなかった。 そこで、オクルディンと何らかの意味で相互作用する膜蛋白質を探すという方向で、このパラドックスを解こうと考えた。 yeast
two-hybrid法や免疫沈降法を試みたが成功せず、上記のジャンクションの単離分画に濃縮する膜蛋白質の中で、種々の条件下(超音波破壊や蔗糖密度勾配遠心)でオクルディンと挙動をともにするものを探すことにした。 その結果、最終的に、電気泳動上23kDaの分子量を示す蛋白質が候補として残ったので、そのアミノ酸配列を決定したところ、2つのESTクローンに一致した。 これらのESTクローンから全長の遺伝子を単離したところ、互いにアミノ酸レベルで約30%のホモロジーを示す2種類の23kDa蛋白質をコードするcDNAが同定された(もともとの23kDaのバンドが少なくとも2種類以上の蛋白質の混合物だったことになる)。 おもしろいことに、これらの蛋白質はそのアミノ酸配列から、やはり4回膜貫通型の内在性膜蛋白質と思われたが、オクルディンとは全くホモロジーを示さなかった
(図3)。  いずれの蛋白質もタグをつけて上皮細胞に発現させるとTJストランドに取り込まれることが分かったので、この時点でクローディン−1と−2(claudin-1,-2:ラテン語のclaudere、閉じるの意、から)と名付けた12)。
いずれの蛋白質もタグをつけて上皮細胞に発現させるとTJストランドに取り込まれることが分かったので、この時点でクローディン−1と−2(claudin-1,-2:ラテン語のclaudere、閉じるの意、から)と名付けた12)。
クローディン−1または−2をTJを持たないマウスL線維芽細胞に強制発現させると、いずれの場合も、もともと細胞間接着活性を示さないL細胞が互いに強固に接着するようになった13)。 さらに細胞間に巨大なTJストランドネットワークが形成された(図4)。 オクルディンをL細胞に発現させてもこのようなネットワークは形成されないが、クローディンと同時に導入すると、クローディンによって形成されたストランドにオクルディンが組み込まれた14)。
5.クローディン遺伝子ファミリー
クローディン−1と−2の存在は、クローディン遺伝がファミリーを形成していることを意味していた。 そこでデータベースを調べてみると、クローディン−1と−2に似たアミノ酸配列が沢山登録されていた。
これらの配列をもとに、それぞれをコードする遺伝子を同定していったところ、最終的にクローディンファミリーはマウスで少なくとも15種類のメンバーからなることが明らかになった15,16)。
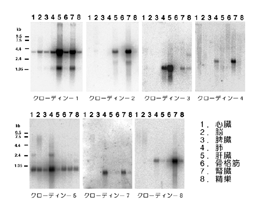 図5は、クローディン−1から−8までの各臓器における発現をノザンブロットにより調べたものであるが、それぞれのクローディンが複雑な組み合わせで各臓器で発現しているのが分かる。 例えば、クローディン−1は比較的多くの臓器で発現しているが、特に肝臓と腎臓に多い。 一方、クローディン−3の発現は肺と肝臓に限られている。 また、クローディン−6は成体では発現が見られず、胎児では多くの臓器に発現しているようである。
図5は、クローディン−1から−8までの各臓器における発現をノザンブロットにより調べたものであるが、それぞれのクローディンが複雑な組み合わせで各臓器で発現しているのが分かる。 例えば、クローディン−1は比較的多くの臓器で発現しているが、特に肝臓と腎臓に多い。 一方、クローディン−3の発現は肺と肝臓に限られている。 また、クローディン−6は成体では発現が見られず、胎児では多くの臓器に発現しているようである。
いくつかの特殊な細胞は、特殊なクローディンを発現しているということも、最近明らかになってきた。 例えば、図5に見られるようにクローディン−5は、脳、心筋、骨格筋といった上皮細胞を含まない臓器にも多く発現している。 このことから、このクローディンは血管の内皮細胞に発現しているのではないかと考え、特異抗体の作製を試みた。その結果、予想通り、クローディン−5が血管特異的カドヘリンであるVEカドヘリンとともに、血管の内皮細胞間に濃縮していることが明らかになった17)(図6)。
今のところ、他の種類のクローディンの発現は血管内皮細胞には見られていないので、 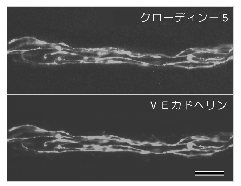 クローディン−5が血管の透過性を規定する重要な分子である可能性が高い。 もう一つの例として、クローディンー11が挙げられる。 このクローディンは、ノザンブロットでは主に脳と精巣に発現している。 やはり特異抗体を作製して調べたところ、脳ではミエリンの細胞膜間の特殊なTJを、精巣ではセルトリ細胞間のよく発達したTJを構成していることが分かった18)。 すなわち、このクローディンは、有髄神経における跳躍伝導や、精巣における血管精巣バリアーにとって重要な分子であることが示唆された。
クローディン−5が血管の透過性を規定する重要な分子である可能性が高い。 もう一つの例として、クローディンー11が挙げられる。 このクローディンは、ノザンブロットでは主に脳と精巣に発現している。 やはり特異抗体を作製して調べたところ、脳ではミエリンの細胞膜間の特殊なTJを、精巣ではセルトリ細胞間のよく発達したTJを構成していることが分かった18)。 すなわち、このクローディンは、有髄神経における跳躍伝導や、精巣における血管精巣バリアーにとって重要な分子であることが示唆された。
6.タイトジャンクションストランドの分子構築
前述したように、2本のTJストランドが側面で対合することによりTJのキッシングポイントが形成されている。
一方、L細胞にトランスフェクションする実験により、クローディンが線状に重合してTJストランドが形成されることが証明されている13)。 複数の種類のクローディンが一つの細胞に共発現しているとなると、対合している2本のストランドの中にこれらのクローディンはどのように組み込まれているのであろうか? 問題が複雑になるので、図7では2種類のクローディンが共発現している場合について考えてみる。
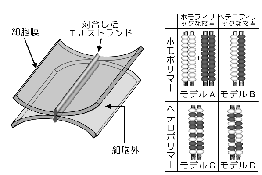 まず、それぞれのストランドが同一のクローディンからなるホモポリマーであるケースと、2種類のクローディンが共重合して(ヘテロポリマー)一本のストランドを形成しているケースが考えられる。 さらに、向かい合うストランドどうしが対合する際、同じクローディンどうしが接着するケース(ホモフィリックな接着)と、異なるクローディンどうしも接着できるケース(ヘテロフィリックな接着)が考えられる。 これらをまとめると、単純にはAからDまでの4種類のモデルが考えられる。 実際のTJでは、どのモデルが当てはまるのであろうか?
まず、それぞれのストランドが同一のクローディンからなるホモポリマーであるケースと、2種類のクローディンが共重合して(ヘテロポリマー)一本のストランドを形成しているケースが考えられる。 さらに、向かい合うストランドどうしが対合する際、同じクローディンどうしが接着するケース(ホモフィリックな接着)と、異なるクローディンどうしも接着できるケース(ヘテロフィリックな接着)が考えられる。 これらをまとめると、単純にはAからDまでの4種類のモデルが考えられる。 実際のTJでは、どのモデルが当てはまるのであろうか?
肝臓の実質細胞では、少なくともクローディン−1、−2、−3の3種類のクローディンが共発現している。 電子顕微鏡レベルの抗体染色では、これらのクローディンがTJストランドに比較的均一に混ざり合っている、すなわち、ヘテロポリマーを形成しているようにみえる。 実際、
L細胞にこれらのクローディンのうち、任意の2種類を共発現させると、確かにヘテロポリマーを作ることが証明された19)。 もちろん、クローディン−1や−2を単独で発現させてもTJストランドが再構成されるので、ホモポリマーも作り得る13)。 そこで、次に、クローディン−1だけ、またはクローディン−2だけを発現させたL細胞(それぞれC1L細胞およびC2L細胞)を、クローディン−3だけを発現させたL細胞(C3L細胞)と混ぜて培養してみたところ、C1L/C3L細胞間にもC2L/C3L細胞間にもよく発達したTJストランドネットワークが形成された。 すなわち、クローディン−1と−3、クローディン−2と−3は、それぞれヘテロフィリックに接着することにより対合したTJストランドを形成することができるのである。 したがって、4つのモデルのうち、もっとも複雑なモデルDが実際のTJで起きていると結論された19)。 すなわち、「2種類以上のクローディンが共重合してヘテロポリマーであるTJストランドを形成し、向かい合う細胞膜中のストランドどうしがクローディン間のヘテロフィリックな接着により対合して、細胞膜間の距離をゼロにしているのが、TJである」と結論できる。 ただし、実際にはオクルディンもこのTJストランドに組み込まれており、さらに複雑な分子構築が予想される。 どのようにこれらの蛋白質が配置されてTJストランドが形成されているかは今後の電子顕微鏡などを用いた構造解析を待たなければならない。
7.バリアー機能とクローディン
TJストランドの基本構造がクローディンによって構成されていることは明らかになったが、それでは、このクローディンよりなるTJストランドが上皮細胞や内皮細胞シートのバリアー機能を実際に担っているのであろうか? あるクローディンを上皮細胞に過剰発現させても、TJストランドの数(TJの発達具合)が、それぞれの上皮細胞で何らかの機構で規定されているらしく、TJストランドの数が著しく増えてバリアー機能が極端に上昇することはないようである。 一方、クローディンの発現を抑える方向の実験も、それぞれの上皮細胞に幾種類ものクローディンが発現しているために易しくないが、最近、腸内細菌の毒素を利用するというユニークな方法で、バリアー機能とクローディンの関係が明瞭に示された20)。
上述したように、クローディン−1と−2に似た分子をデータベースから探した時に、腸内細菌(Clostridium
perforingens)のペプチド性毒素のレセプター(CPE−R)21)も、クローディンファミリーの一員であるということに気付いた(現在ではクローディン−4と呼ばれている)。 この毒素は、C末端半分でレセプターに結合し、N末端半分で細胞膜に穴をあけると考えられていたので、まず、C末端側半分に相当するペプチド(C−CPE)を大腸菌で作製し、このペプチドが培養上皮細胞であるMDCK細胞のバリアー機能にどのような影響を与えるかを調べた。
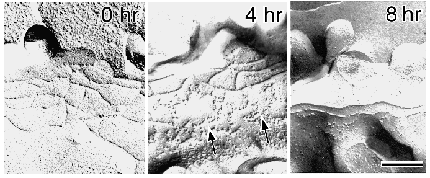 MDCK細胞には、おもに、クローディン−1と−4が発現していたが、 C−CPEはクローディン−1には結合せず、クローディン−4にだけに結合することが確認された。
興味深いことに、MDCK細胞をC−CPE存在下で培養すると、 1時間以内にそのTJからクローディン−4のみが選択的に消え始め、4時間位でクローディン−1のみからなるTJに変化した。 これに平行して、電気抵抗として測定されるバリアー機能は極端に低下した。 この時、TJストランドは、
C−CPEの存在下で、急速に溶けたように壊れ始め、最終的にストランドの数が半分以下に減ることが分かった(図8)。 このペプチドを洗い流すと、再びクローディン−4がTJに濃縮し始め、バリアー機能も回復した。 以上の結果は、クローディンがTJストランドを形成することにより、上皮細胞や内皮細胞シートのバリアー機能を直接担っていることを初めて示したものである。
MDCK細胞には、おもに、クローディン−1と−4が発現していたが、 C−CPEはクローディン−1には結合せず、クローディン−4にだけに結合することが確認された。
興味深いことに、MDCK細胞をC−CPE存在下で培養すると、 1時間以内にそのTJからクローディン−4のみが選択的に消え始め、4時間位でクローディン−1のみからなるTJに変化した。 これに平行して、電気抵抗として測定されるバリアー機能は極端に低下した。 この時、TJストランドは、
C−CPEの存在下で、急速に溶けたように壊れ始め、最終的にストランドの数が半分以下に減ることが分かった(図8)。 このペプチドを洗い流すと、再びクローディン−4がTJに濃縮し始め、バリアー機能も回復した。 以上の結果は、クローディンがTJストランドを形成することにより、上皮細胞や内皮細胞シートのバリアー機能を直接担っていることを初めて示したものである。
8.paracellular チャネルとクローディン
異なるクローディン間でヘテロフィリックな接着ができると述べたが、これは単純化しすぎていることも分かってきた。 上述したようにC1L細胞とC3L細胞の間、またはC2L細胞とC3L細胞の間にはヘテロフィリックな接着により立派なTJが形成されるが、C1L細胞とC2L細胞を混合培養しても、その間にはTJストランドが形成されないのである19)。 すなわち、クローディンの組み合わせによって、その接着強度に明らかな差があるようにみえる。 そのようなことを前提にして、モデルDを眺めてみると、このTJという構造はなかなか複雑なシステムであるということに気付く。 例えば、クローディンー1とクローディンー3でモデルDのような対合する2本のストランドを形成している場合と、クローディンー1とクローディンー2で形成している場合を考えてみよう(図9)。
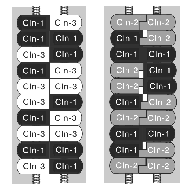 前者ではクローディンー1とー3のヘテロポリマーが対合するので、クローディンー1どうしおよびクローディンー3どうしのホモフィリックな接着と、クローディンー1とクローディンー3のヘテロフィリックな接着が混在するが、いずれも比較的強く接着する。 しかし、後者では、クローディンー1どうしおよびクローディンー2どうしのホモフィリックな接着は強いが、強制的に向かい合わされたクローディンー1とクローディンー2は強くは接着できない。 したがって、前者のTJの方が後者より強いバリアー機能を示すことが期待できる。 ぞれぞれ単独でもTJストランドを形成できる15種類ものクローディンが存在する意味は、このようなところにあるのではないだろうか? そのTJに含まれるクローディンの種類と混合の割合によって、対合するTJストランド間に作る“穴”の数と性質を変えて、TJのバリアー機能を巧みに調節しているのではないだろうか?
前者ではクローディンー1とー3のヘテロポリマーが対合するので、クローディンー1どうしおよびクローディンー3どうしのホモフィリックな接着と、クローディンー1とクローディンー3のヘテロフィリックな接着が混在するが、いずれも比較的強く接着する。 しかし、後者では、クローディンー1どうしおよびクローディンー2どうしのホモフィリックな接着は強いが、強制的に向かい合わされたクローディンー1とクローディンー2は強くは接着できない。 したがって、前者のTJの方が後者より強いバリアー機能を示すことが期待できる。 ぞれぞれ単独でもTJストランドを形成できる15種類ものクローディンが存在する意味は、このようなところにあるのではないだろうか? そのTJに含まれるクローディンの種類と混合の割合によって、対合するTJストランド間に作る“穴”の数と性質を変えて、TJのバリアー機能を巧みに調節しているのではないだろうか?
このような仮説によく合致する事実が、ごく最近、常染色体劣性遺伝形式をとる低マグネシウム血症の原因遺伝子の解析から、明らかにされた22)。 マグネシウムイオンは、腎臓の糸球体で一旦濾過され、尿中に出た後で、その大部分がヘンレの上行脚で再吸収されるが、これらの家系の患者では、この再吸収が全く行われない。 そのため、血中のマグネシウムイオン濃度が低下するという遺伝病である。 マグネシウムイオンの再吸収は、上行脚の上皮において、transcellular
pathwayではなく、大部分がpracellular pathwayを介する受動的な輸送によって担われていることが知られていた。 その原因遺伝子がポジショナルクローニング法により同定され、その遺伝子産物のアミノ酸配列が推定されてみると、驚いたことにクローディンファミリーに属することが明らかになったのである。 このクローディンは、それまで同定されていた15種類のクローディンのいずれとも一致せず、クローディンー16(遺伝子を同定したグループはparacellin-1
と呼んでいるが)というべきものであった。 このクローディンは、ヘンレの上行脚だけに発現している特殊なクローディンで、その発現がなくなると(または機能が抑制されると)paracellular
pathwayを介したマグネシウムイオンの輸送が阻害されることから、このクローディンがTJストランドの中で、マグネシウムイオンを比較的選択的に通すチャネル(穴)を形成していると考えられた。 どのようにしてこのクローディンがチャネルを形成するかは今後の問題であるが、上述したように、もし、このクローディンがヘンレの上行脚の上皮細胞に発現している他のクローディンとヘテロフィリックな接着をする上で相性が悪いと仮定すると、対合する2本のTJストランド間にクローディンー16(paracellin-1)とその相性の悪いクローディンとによって“穴”が作られ、そこをマグネシウムイオンが通ることは容易に想像できる。 このような発見により、古くからその存在が予想されていたparacellular
チャネルの実体が、クローディンそのものであることが示唆された。
9.タイトジャンクション研究の今後:まとめにかえて
この総説では、我々の研究の流れを追って、TJの接着分子、すなわちTJストランドを形成する内在性膜蛋白質について、現在までに明らかになったことをまとめてみた。 細胞間接着という現象が分子の言葉で語られるようになってから久しいが、TJという特殊な細胞間接着を司る分子の同定は遅れていた。 クローディン分子のかなりの部分が細胞膜内に埋まっているために、抗体による分子の同定や機能阻害が難しかったことも一因であったように思われる。 クローディン分子群は、発見されてから日が浅いために、まだ不明な点が多い。 しかし、TJストランドの基本的な分子構築が明らかにされた今、TJの研究はいくつかの方向に大きく発展するものと期待される。 今後の発展の方向を議論することで、この総説のまとめとしたい。
まず、第一に、本総説で詳しく述べてきたように、TJのバリア機能の分子レベルでの理解が深まるであろう。 TJのバリア機能、およびその調節機能が、多細胞生物の個体形成の上でどのように重要な役割を果たしているかが、それぞれのクローディン遺伝子のノックアウトマウスを作製することにより、明らかにされるであろう。
そして、バリアー機能の異常とさまざまな疾患・病態との関係も明らかになるであろう。 さらに、Clostridium
perforingensの毒素の実験でも明らかなように、TJのバリアー機能を人為的に操作する方法が確立され、脳血管関門などを一時的に破壊することが可能となり、ドラッグデリバリー法の開発の上でも大きな進歩をもたらすであろう。 すなわち、これまでのtranscellular
pathwayの生理学に対して、全く新しいparacellular pathwayの生理学の発展とその応用が期待できる。
第二に、ここでは全く触れなかったことであるが、上皮細胞や内皮細胞の極性形成におけるTJの役割の理解も分子レベルで深まるであろう。 TJストランドは、アピカル膜ドメインとバソラテラル膜ドメインの間に、オイルフェンスのように張り巡らされているため、二つのドメインを分ける役割(フェンス機能)を果たしていると想定されてきた2)。 この想定そのものが正しいかどうか、クローディンが同定された今、実験的に検証できるであろう。 また、TJストランドの細胞質側には、オクルディン・クローディンと直接結合するZO−1、ZO−2、ZO−3などの裏打ち蛋白質の他に23,24)、種々の上皮細胞の形態形成シグナルを担うと思われる因子が集積していることが最近明らかになりつつある25)。 このようなシグナル伝達のセンターの一つとしてのTJの役割の解析も今後の重要な方向であろう。
一方で、オクルディンの機能は依然として謎に包まれている。 オクルディンノックアウトマウスは、一見正常に生まれるが、その後の成長が遅く、胃、唾液腺、脳、骨などにそれぞれ特徴的な病変を生じ、子孫を残すことができない(斉藤ら、投稿準備中)。 このマウスは、
まだ我々が全く知らない重要な役割をTJが果たしていることを強く示唆している。 TJの周辺には、まだまだ、多くの謎解きの楽しみが残っている。
この研究は、都臨床研・国立生理研以来の仲間であり、現在の我々の研究室のスタッフである月田早智子、米村重信、永渕昭良、伊藤雅彦の各博士が進めてきた細胞間接着装置の分子生物学的研究の延長線上に、各博士の協力により生まれてきたものであり、ここに深く感謝します。 また、ここに紹介した研究の多くは、大学院生により進められたものであることを記し、感謝の意を表します。
(補)本文を書き上げてから印刷までの間に、クローディン−11のノックアウトマウスが報告された [Grow,A., Southwood,C.M., Li,J.S., Pariali,M., Riordan,G.P., Brodie,S.E., Danias,J., Bronstein,J.M., Kachar,B. & Lazzarinin,R.A. (1999) Cell 99,649-659]。 クローディン−11はOSP(oligodendrocyte specific protein)として1996年に遺伝子として報告されていたものであるが、この遺伝子産物がTJの構成因子であることが分かる以前から、この遺伝子の機能解析の一環としてアメリカのグループによりノックアウトマウスの作製が進められていたらしい。 本文中で述べたように、このクローディンは中枢神経のミエリンと精巣のセルトリ細胞のTJに特異的に存在している特殊なものであることを我々は報告していたが18)、予想通りこのマウスではこれらの細胞からTJが消えており、有髄神経の伝導速度の低下と精子形成不全が観察された。 これがクローディンファミリーのメンバーのノックアウトマウスとしては最初の報告であり、クローディンの重要性が個体レベルで証明されたことになる。 また、2000年1月の段階で、クローディンは18種類まで同定されている。
文 献
1) Claude, P. (1978) J. Membr. Biol. 10, 219-232
2) Gumbiner, B. (1993) J. Cell Biol. 123, 1631-1633
3) Farquhar, M.G., & Palade, G.E. (1963) J. Cell Biol.
17, 375-412
4) Staehelin, L.A. (1974) Int. Rev. Cytol. 39, 191-283
5) Pinto da Silva, P., & Kachar, B. (1982) Cell 28,
441-450
6) Tsukita, Sh., & Tsukita, Sa. (1989) J. Cell Biol. 108,
31-41
7) Itoh, M., Nagafuchi, A., Yonemura, S., Kitani-Yasuda, T., Tsukita,
Sa., & Tsukita, Sh. (1993) J. Cell Biol. 121,
491-502
8) Furuse, M., Hirase, T., Itoh, M., Nagafuchi, A., Yonemura,
S., Tsukita, Sa., & Tsukita, Sh. (1993) J.Cell Biol.
123, 1777-1788
9) Ando-Akatsuka, Y., Saitou, M., Hirase, T., Kishi, M., Sakakibara,
A., Itoh, M., Yonemura, S., Furuse, M., & Tsukita, Sh. (1996)
J. Cell Biol. 133, 43-47
10) Matter, K., & Balda, M. (1999) Int. Rev. Cytol. 186,
117-146
11) Saitou, M., Fujimoto, K., Doi, Y., Itoh, M., Fujimoto, T.,
Furuse, M., Takano, H., Noda, T., & Tsukita. Sh. (1998) J.Cell
Biol. 141, 397-408
12) Furuse, M., Fujita, K., Hiiragi, T., Fujimoto, K., & Tsukita,
Sh. (1998) J. Cell Biol. 141, 1539-1550
13) Kubota, K., Furuse, M., Sasaki, H., Sonoda, N., Fujita, K.,
Nagafuchi, A., & Tsukita, Sh. (1999) Curr Biol. 9,
1035-1038
14) Furuse, M., Sasaki, H., Fujimoto, K., & Tsukita, Sh. (1998)
J. Cell Biol. 143, 391-401
15) Morita, K., Furuse, M., Fujimoto, K., & Tsukita, Sh. (1999)
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96, 511-516
16) Tsukita, Sh., & Furuse, M. (1999) Trend. Cell Biol.
9, 268-273
17) Morita, K., Sasaki, H., Furuse, M., & Tsukita, Sh. (1999)
J.Cell Biol. 147, 185-194
18) Morita, K., Sasaki, H., Fujimoto, K., Furuse, M., & Tsukita.
Sh. (1999) J. Cell Biol. 145, 579-788
19) Furuse, M., Sasaki, H., & Tsukita, Sh. (1999) J. Cell
Biol. in press.
20) Sonoda, N., Furuse, M., Sasaki, H., Yonemura, S., Katahira,
J., Horiguchi, Y., & Tsukita, Sh. (1999) J. Cell Biol.
147, 195-204
21) Katahira, J., Inoue, N., Horiguchi, Y., Matsuda, M., &
Sugimoto, N. (1997) J. Cell Biol. 136, 1239-1247
22) Simon, D.B., Lu, Y., Choate, K.A., Velazquez, H., Al-Sabban,
E., Praga, M., Casari, G., Bettinelli, A., Colussi, G., Rodriguez-Soriano,
J., McCredie, D., Milford, D., Sanjad, & S., Lifton, R.P.
(1999) Science 285, 103-106
23) Furuse, M., Itoh, M., Hirase, T., Nagafuchi, A., Yonemura,
S., Tsukita, Sa., and Tsukita, Sh. (1994) J. Cell Biol. 127,
1617-1626
24) Itoh, M., Furuse, M., Saitou, M., Morita, K., Kubota, K.,
and Tsukita, Sh. (1999) J. Cell Biol. in press
25) Tsukita, Sh., Furuse, M., & Itoh, M. (1999) Curr. Opin.
Cell Biol. 11, 628-633